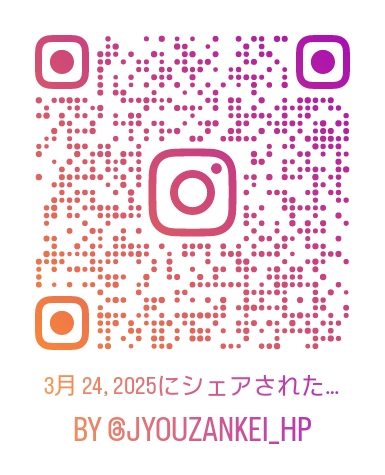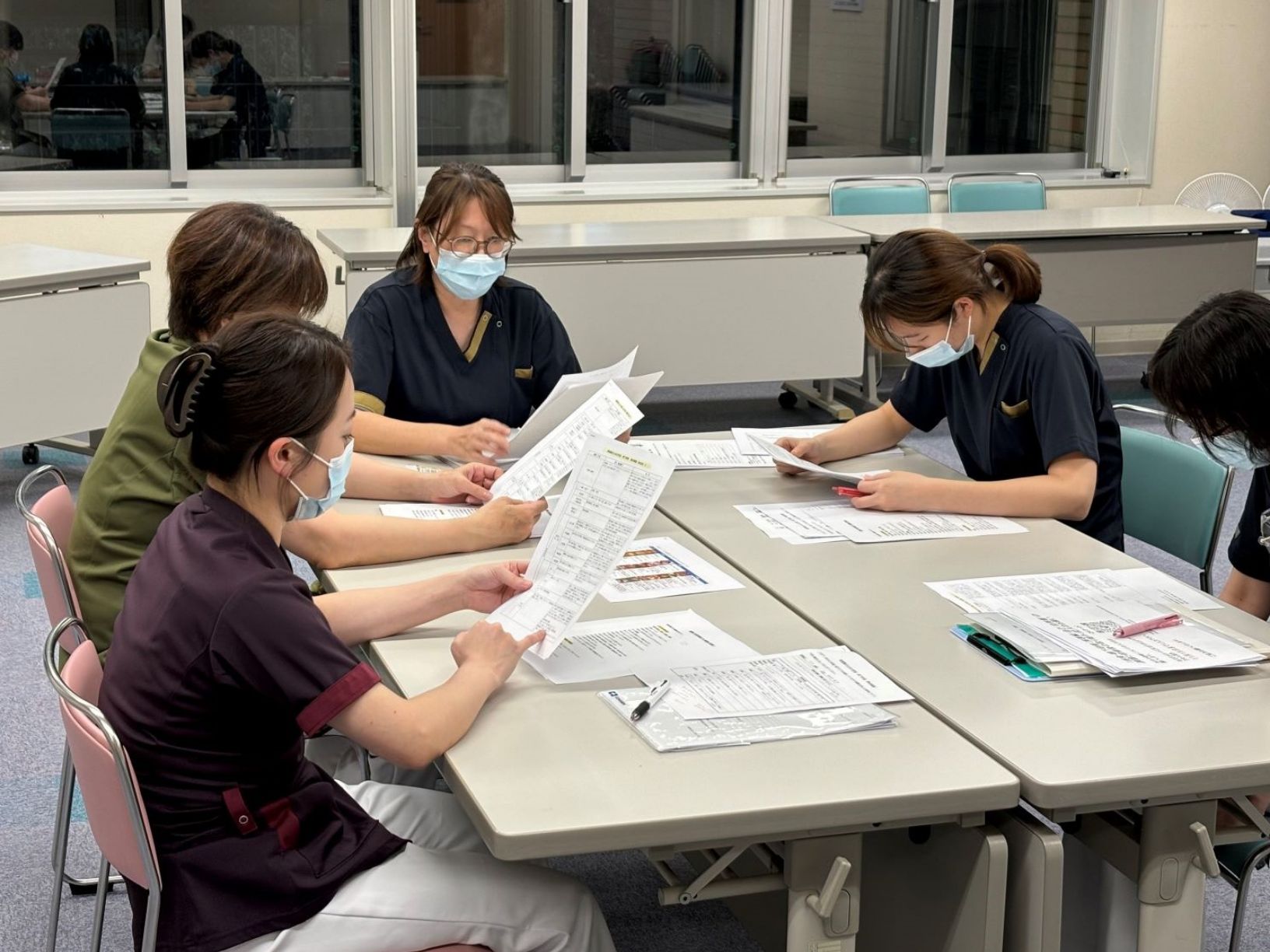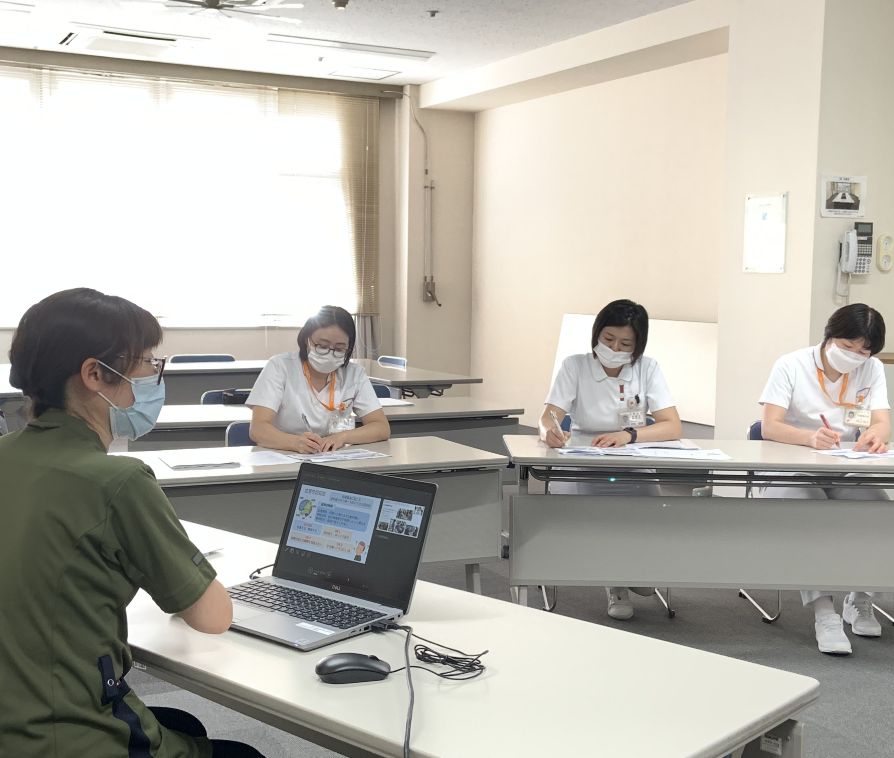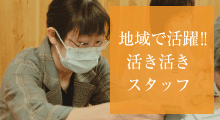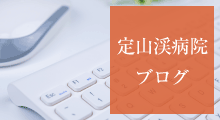�@�����C
2025�N�x�� ���C�X�P�W���[��
����ڕW
- ���҂̈ӎv������x���邽�߂ɕK�v�Ȓm���E�Z�p�E�ԓx���w�K���������
- ���҂̏�Ԃ𐳂����A�Z�X�����g���A�œK�Ȏ��H�����邽�߂̐��I�m���E�Z�p���w�K���������
- ���C��ʂ��āA�`�[���̈���Ƃ��Ă̎��Ȃ̖�����F������
2025�N�x�� ���C���e
| ���C�� | �Ώ� | ��ް ���� |
�ړI | �˂炢 | ���� | ��u���̊��z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �V�l�Ō�t | ||||||
| �V�l�Ō�E�� ���C�i�T���j | �Ō� | �Տ�����ő����Ɏ��H���邱�Ƃ�������{�I�ȊŌ�Z�p���A���������@�Ŏ��H�ł���悤�ɂȂ� | 1.�Ō�Z�p�̊�{�I�Ȓm���𗝉����邱�Ƃ��ł��� 2.�K�v���i�𗝉����A���������邱�Ƃ��ł��� 3.���߂�ꂽ�菇�ǂ���A���������@�ŊŌ�Z�p�����{���邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �Ee-���[�j���O��p������b�m���̊w�K �E�V�~�����[�^�[�ł̉��K�@�Ȃ� �y���K���e�z �E�ڏ�E�ڑ� �E���ނ��� �E�̈ʕϊ� �E�H��� �E���o�P�A �E�o�ljh�{ �E�A�����u�J�e�[�e���}�� �E�z�� �E�̌��E�Ö����NJm�� |
4�� |
|
|
| �V�l�Ō�E��I��̫۰���C �iKYT���C�j | �Ō� | ��Ì���ɐ��ފ댯���w�сA���҂̍s����\�����ւ��K�v���𗝉��ł��� | 1. ��Ì���ɂ�����댯�𗝉��ł��� 2. �j�x�s�̓��e�������ł��� 3. �a���łǂ̂悤�ɂj�x�s�����p�ł��邩�l���邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
7�� | ||
| �V�l�Ō�E�����C�i�U���j | �Ō� | �a�Ԃɍ��킹���H���A�r���A���J�A�����E�畆�P�A�A�ċz�P�A�A�^��A���̍̎�A���ۑ���A�E�Ɗ֘A���̑Ή��ɂ��ė����ł��� | �y���C���@�z e-���[�j���O��p�������Ȋw�K |
8���` 11�� | ||
| �V�l�Ō�E�� �U��̫۰���C | �Ō� | ���҂̌ʐ��ɂ��čl���Ō삷���ʼn������ׂ����Ȃ̉ۑ�𖾂炩�ɂ��� | 1.���҂̏�Ԃ𑨂��Ō���l���邱�Ƃ��ł��� 2.���҂Ɏ��{���Ă���P�A�̍������l���邱�Ƃ��ł��� 3.���E1�N��ɂǂ̂悤�ȊŌ�t�ɂȂ�A�ǂ�ȊŌ�����������l���邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �O���[�v�f�B�X�J�b�V�����i���ጟ���j |
11�� | ||
| �V�l�Ō�E�����C�i�V���j | �Ō� | �a�ԁE�a��ɍ��킹���×{�x���A���I�ȉ�E�Ǘ��E���u�A�������̌��A��܁ABLS�A���S���̃P�A�ɂ��ė����ł��� | �y���C���@�z e-���[�j���O��p�������Ȋw�K |
12���` 3�� | ||
| �V�l�Ō�E�� �V��̫۰���C | �Ō� | �u�Ȃ肽�������v�ɂȂ邽�߂̍���̎�g�ɂ��čl���� | �y���C���@�z �t���[�����[�N ���k�� |
2�� | ||
| ۰ð����C | �Ō� | �������ł̊Ō��̌����A����������у��[�e�[�V�����敔���̓����ɂ��ė�����[�߂邱�Ƃ��ł���B�܂��A���g�̊Ō�X�L������ɂȂ���@��Ƃ��邱�Ƃ��ł��� | 1. �������ł̊Ō�̌��̒��ŁA�������Ƃ̈Ⴂ�⋤�ʓ_�A���ғ����𗝉����� 2. �������ł̊Ō�̌���ʂ��āA���g�̊Ō�X�L����U��Ԃ�@��Ƃ��� �y���C���@�z �������ł̎����o�� |
8�� �i2024�N�x�V���E���Ώہj | ||
| ̫۰���ߌ��C�T | �Ō� ���E�� | �V���E���Ƃ��Ċ����邱�Ƃ����R�Ɍ�荇�����ŁA���育�Ƃ��肪�������L���A�E����z���đ��k��������W�����ł��邱�ƂŁA�A�J���͂ɂȂ��邱�Ƃ��ł��� | 1. �s����炳�����z���邽�߂̐�y�����̒m�b���w�Ԃ��Ƃ��ł��� 2. ���ԂƂ��đ��k��������W�������邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �E���E�퍇�����C �E��y�E���̑̌��k�u �E�O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
6�� | ||
| ̫۰���ߌ��C�U | �Ō� ���E�� | 1. ���ԂƋ��ɁA���N�x�̊w�т�o����U��Ԃ�A���g�̍���̃L�����A�ɂ��čl���� 2. �Q�N�ڂ��}����ɂ������Ă̐S�\��������ɂ��Č��ꉻ���� �y���C���@�z �E���E�퍇�����C �E�O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
3�� | |||
| �Ō�ߒ����C | �Ō� | ���ጟ����ʂ��Ď��g�̊Ō���H�ɂ����鋭�݁E��݂�m�鎖�ŁA�Ō�͌���ɂȂ���@��Ƃ��� | 1.�Տ���ʂ�z�肵�����ጟ����ʂ��A���g�̊Ō���H��U��Ԃ�A���҂ɂƂ��čœK�ȊŌ���l���邱�Ƃ��ł��� 2.���g�̋��݁E��݂����A����̂��ǂ��Ō���H�ɂȂ���@��Ƃ��� �y���C���@�z �E�u�` �E�O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
������ | ||
| ���_�[�� | ||||||
| �t�B�W�J���A�Z�X�����g���C | �Ō� | �T | ������ | ������ | 10�� | |
| �ېH���������C �i��b�ҁj | �Ō� ��� ���E�� | �T | ���S�ȐH���������s�����߂ɕK�v�Ȋ�b�I�m���Ƒԓx���K������ | 1. ������u�H�ׂ�v���Ƃ̈Ӌ`�𗝉����� 2. �ېH�E�����̃��J�j�Y���𗝉����� 3. �ېH�E������Q�������҂ɋN����₷�����X�N�Ƃ��̏Ǐ�𗝉����� 4. ���S�ɐH������s�����߂̕��@�𗝉����� �y���C���@�z �E�u�` �E���K |
9�� | |
| �ېH���������C �i���H�ҁj | �Ō� | �T | �ېH�E�����̍����ɂ��ĐU��Ԃ�A���S�ȐH���������s�����߂̒m���Ƒԓx���K������ | 1. ��u���̌o����������ƂɁA���̑ΏۂɕK�v�ȃA�Z�X�����g�A�P�A���@���v�l���邱�Ƃ��ł��� 2. ���C�ł̊w�т��A���H�ɓK�����邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �E�u�` �E�O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
11�� | |
| �����ײ̹����C | �Ō� ��� ���E�� | �U | �I�����ɂ��銳�ҁE�Ƒ��ւ̑�������ѐl���d�����P�A�ɂ��ė������� | 1. �I�����̊��ҁE�Ƒ��P�A�ɂ��ė������� 2. �A�h�o���X�E�P�A�E�v�����j���O�iACP�j�̊�{�T�O�ɂ��ė������� 3. ���g���l����I�����P�A�ɂ��ďq�ׂ邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �E�u�` �E�O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
7�� | |
| �މ@�x�����C �i���މ@�x���j | �Ō� ��� ���E�� | �U | �މ@�x���ɂ��Ă̊�{���w�сA�Ō�E�Ƃ��Ďx���̓��e����H���w�Ԃ��ƂŁA��葁������މ@�x�����H���s���A�����ł����S�E���S�Ŋ��Җ����̍����×{�x���ɂȂ��邱�Ƃ��ł���B | 1. �u�`��ʂ��āA�މ@�x���̊�{�I�Ȓm���邱�Ƃ��ł��� 2. �Ō쌻��ł̑މ@�x���̎��H���C���[�W���A����̗×{�x���ɂȂ��邽�߂̈ꏕ�Ƃ��邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �E�u�` �E�O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
11�� | |
| �މ@�x�����C �i�ݑ�×{�x���j | �Ō� ��� ���E�� | �U | �މ@�x���Ɋւ����{�I�Ȓm����m��A�x���҂Ƃ��Ă̖�������H�𗝉����邱�ƂŁA�x���̕K�v�Ȋ��ҁE�Ƒ����ւ̑Ή��Ɋ��������Ƃ��ł��� | 1. �މ@�x���Ɋւ����{�I�Ȓm���◬��ɂ��ė������邱�Ƃ��ł��� 2. �a���Ō�t�Ƃ��āA���g�⑽�E��̖����A���H���e�𗝉����邱�Ƃ��ł��� 3. �x���̕K�v�Ȋ��ҁE�Ƒ����ɑ��āA�K�v�Ȏx�����C���[�W���邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �E�u�` �E�O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
12�� | |
| ���\�[�X | ||||||
| �F�m�ǃP�A���C �i��b�ҁj | �Ō� ��� | �T | ���@�œ����Ō�E���E�Ƃ��āA�F�m�ǂɂ��Ă̒m�����K�����A�Ώێ҂Ɍ���Ă���Ǐ�ɂ��ăA�Z�X�����g���o���A�Ǐ�ɉ������Ō�A��삪�ł��� | 1. �F�m�ǂ̑�\�I��4�̎����𗝉����� 2. 4�̎����̊Ō�E���̓����𗝉����� �y���C���@�z �E�u�` |
6�� | |
| �F�m�ǃP�A���C �i���H�ҁj | �Ō� ��� | �U | ���@�œ����Ō�E���E�Ƃ��āA�F�m�ǂɂ��Ă̒m�����K�����A�Ώێ҂Ɍ���Ă���Ǐ�ɂ��ăA�Z�X�����g���o���A�Ǐ�ɉ������Ō�A��삪�ł��� | 1. �F�m�ǂ̐l�̗�����[�߁A�Ή����@���l�����H�ł��� 2. �R�~���j�P�[�V�������@�ɂ��ė������A���H�ł��� �y���C���@�z �E�u�` �E�O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
10�� | |
| �L�����A�x�� | ||||||
| ���E���Z�p���C | ��� | ����ʂɂ�����ϗ��I�ւ���U��Ԃ�A����̃P�A�̏�ʂɊ��������Ƃ��o����B | ���ނ����ɂ�������Z�p�Ɨϗ��I�z���ɂ��ė����ł���B �y���C���@�z �E���K �E�O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
10�� | ||
| ��ر�x�����C�T | �Ō� | �U | �Ō�E�Ƃ��Ắu�L�����A�v�ɂ��Ă̊�{�T�O��m��A���g�̊Ō�E�L�����A���l����@��Ƃ��邱�Ƃ��ł��� | 1.�u�`��ʂ��āA���g�̊Ō�E�L�����A��U��Ԃ邱�Ƃ��ł��� 2.���g�̋��݂��肪�������A����̊Ō�E�L�����A�`���ɂȂ���@��Ƃ��邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �E�u�` �E�l���[�N |
8�� | |
| ��ر�x�����C�U �i�l�ތ𗬌��C�j | �Ō� ��C | �U | 1.�}�������疝�����A�ݑ�×{���̑��@�\�^�Ō�i�������͋}�����Ō�j�̌���ɐG��A������(�{��)�Ƃ̘A�g���l���鎖�ŁA���X���[�Y�ȊŌ�A�g�����H�ł��� 2.���҂̑މ@��̗×{�����̏���m�邱�ƂŁA�e�����҂Ƃ��Ă̊��ҁf�̎��_�ŊŌ�����H�ł��� 3.���g�̊Ō�̐U��Ԃ�̋@��Ƃ��A����̃L�����A�f�U�C����`���ꏕ�Ƃ��邱�Ƃ��ł��� |
1.�������i�{�݁j�ƘA�g���Ë@�ւ̊Ō�Ƃ̂Ȃ�����w�Ԃ��Ƃ��ł��� 2.�������E���@�\�^�Ō�i�}�����Ō�j�̎��ۂ��w�Ԃ��Ƃ��ł��� 3.���ꂼ��̋@�\�ɉ��������E��Ƃ̘A�g�݂̍�l��m�邱�ƂŁA�`�[����Âɂ��čl����@��������Ƃ��ł��� 4.���҂̗×{��m��A����̎��g�̊Ō�ɐ��������Ƃ��ł��� �y���C���@�z �E�A�g��Ë@�ւł̃V���h�[���[�N �i3���ԁj |
9�� | |
| ACP���C | �Ō� �t�� ��C | ������ | ������ | 6�� | ||
| �Ō�Ǘ��҃��t���N�V�������C | �Ō� �t�� ��C | 1. �Ō�Ǘ��҂Ƃ��ĕK�v�Ȏp���A��{�I�Ȓm���E�Z�p�Ƃ��Ẵ��t���N�V�����̎�@�Ǝ��H�|�C���g���w�� 2. �u�T�O���v�u���́v��g�ɂ��邱�Ƃ��ӎ����Ċw�� |
�E���t���N�V�����i���ȁj�Ɣ��Ȃ̈Ⴂ��m�� �E�Ō�}�l�W�����g���t���N�V�����̊T�O�𗝉����� �E�Ō�}�l�W�����g���t���N�V�����̎��H���@���w�� �y���C���@�z �Ee-���[�j���O��p�������Ȋw�K �E�O���[�v���[�N |
7�� 8�� 9�� |
||
2024�N�x�� ���C���e
| ���C�� | �Ώ� | ��ް ���� |
�ړI | �˂炢 | ���� | ��u���̊��z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �V�l�Ō�t | ||||||
| �V�l�Ō�E�� ���C�i�T���j | �Ō� | �Տ�����ő����Ɏ��H���邱�Ƃ�������{�I�ȊŌ�Z�p���A���������@�Ŏ��H�ł���悤�ɂȂ� | 1. �Ō�Z�p�̊�{�I�Ȓm���𗝉����邱�Ƃ��ł��� 2. �K�v���i�𗝉����A���������邱�Ƃ��ł��� 3. ���߂�ꂽ�菇�ǂ���A���������@�ŊŌ�Z�p�����{���邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z l e-���[�j���O��p������b�m���̊w�K l �V�~�����[�^�[�ł̉��K�@�Ȃ� | 4�� | �E���ނ��������C�ł�����ۂɂ͗������邱�Ƃ��ł������A���ۂɊ��҂�����{���鎞�͏ł��ĕ��i��Y��Ă��܂����Ƃ��������B �E�Ö����h���s���ہA�S�R�t�����m�F����Ȃ��������ߍ�������K���Ă��������B �E�i�[�V���O�X�L���Ŏ菇���m�F���A��������邾���ł̓C���[�W���ɂ����������Ƃ��A���K���邱�ƂŁA�������ǂ̂悤�ɓ����̂��C���[�W���₷�������ł��B �E���Ȋw�K������A���K���s�����ƂŎ��ۂ̉������̎�Z�ȂǑz�������₷�������ł��B �i�[�V���O�X�L���͓��悪����A�����ŗ���������Ƃ��������邱�Ƃŗ������[�܂�܂����B �������ƈʂł̓��e���Ə������o���āA�o�������Ƃ�a���Ŋw�ׂ�ƍX�ɋL�����蒅���₷���̂��ȂƊ����܂����B
|
|
| �V�l�Ō�E��I��̫۰���C �iKYT���C�j | �Ō� | ��Ì���ɐ��ފ댯���w�сA���҂̍s����\�����ւ��K�v���𗝉��ł��� | 1. ��Ì���ɂ�����댯�𗝉��ł��� 2. �j�x�s�̓��e�������ł��� 3. �a���łǂ̂悤�ɂj�x�s�����p�ł��邩�l���邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� | 7�� |
�E�ł��d�v������|�C���g������߁A���̃|�C���g�ɂ��đ���l���A�����\�Ȃ��̂�I�����Ď��s���Ă������Ƃ��ۑ�����ɂȂ���Ɗw�т܂����B �E���ۂ̊Ō�̏�ʂł��A�ǂ̂悤�Ȋ댯�����݂���̂����l����Ȃ����A�C���V�f���g��A�N�V�f���g���N�����Ȃ��悤�ɍs�����Ă��������Ɗ����܂����B �E�]�|��]���Ȃǖh�����߂ɂ����̊��҂���̏�Ԃ�m�芳�҂���ɂ������P�A�����B �E����ŋN����댯�ɂ��Ċw�сA�Ώێ҂̊댯�Ȏ��ۂ�\�����邱�ƁA�����Ċ댯��h�~��������邱�Ƃ̕K�v�����w�т܂����B |
|
| �V�l�Ō�E�����C�i�U���j | �Ō� | �a�Ԃɍ��킹���H���A�r���A���J�A�����E�畆�P�A�A�ċz�P�A�A�^��A���̍̎�A���ۑ���A�E�Ɗ֘A���̑Ή��ɂ��ė����ł��� | �y���C���@�z l e-���[�j���O��p�������Ȋw�K | 8���` 11�� | �E�O���[�v�����o�[�ƈӌ��������邱�Ƃŗ������[�܂����B �E���҂̏�Ԃɍ��킹�ĕK�v�ȏ��u�̎d����H�v���l���邱�Ƃ��ł��� �E���҂̗���ɗ����Ċւ����l���邱�ƂŁA���҂̏�Ԃɍ��킹���Ō���l���邱�Ƃ��ł��� �E���҂̋C������l���͂ǂ��Ȃ̂����ώ@���邱�Ƃ��d�v���Ɗw�� �E���g�̋Ɩ��s���ł͂Ȃ��A���҂̏�Ԃɍ������Ō�ɂ��čl����[�߂邱�Ƃ��ł��� |
|
| �V�l�Ō�E�� �U��̫۰���C | �Ō� | ���҂̌ʐ��ɂ��čl���Ō삷���ʼn������ׂ����Ȃ̉ۑ�𖾂炩�ɂ��� | 1.���҂̏�Ԃ𑨂��Ō���l���邱�Ƃ��ł��� 2.���҂Ɏ��{���Ă���P�A�̍������l���邱�Ƃ��ł��� 3.���E1�N��ɂǂ̂悤�ȊŌ�t�ɂȂ�A�ǂ�ȊŌ�����������l���邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z �O���[�v�f�B�X�J�b�V�����i���ጟ���j |
11�� | ||
| �V�l�Ō�E�����C�i�V���j | �Ō� | �a�ԁE�a��ɍ��킹���×{�x���A���I�ȉ�E�Ǘ��E���u�A�������̌��A��܁ABLS�A���S���̃P�A�ɂ��ė����ł��� | �y���C���@�z l e-���[�j���O��p�������Ȋw�K | 12���` 3�� | �@�u����ȊŌ�t�ɂȂ肽���v�A�A�u�����F���̎����v�A�B�u���F���z�ƌ����̑���v�A�C�u�ۑ�ݒ�F�����������邽�߂Ɏ��g�ނ��Ɓv�ɂ��āA���O�Ɋe�����t���[�����[�N���s�����k����s�����B���̎����ɂ��Ắu�Ɩ������Z�ŁA���҂ƌ��������Ęb�����ł��Ȃ��B�v�u�m���Ɏ��M���Ȃ����f�ł��Ȃ��B�v�u�i�[�V���O�X�L���Ŋm�F���������ɁA�X�}�z����Ƃ��ڂ��Ă���悤�Ō���̂�����B�v�u�L�^���ߑO���ɏ������Ƃ��ł��Ȃ��B�v�Ƃ��������e�����ʂ��Ă����B�܂��A�ۑ�����Ɍ����Ắu�m����Z�p��g�ɂ��邽�߂ɁA�w�K��[�߂�v�Ƃ����������Q���ґS�����畷���ꂽ�B | |
| �V�l�Ō�E�� �V��̫۰���C | �Ō� | �u�Ȃ肽�������v�ɂȂ邽�߂̍���̎�g�ɂ��čl���� | �y���C���@�z �t���[�����[�N ���k�� |
2�� | ||
| ۰ð����C | �Ō� | �������ł̊Ō��̌����A����������у��[�e�[�V�����敔���̓����ɂ��ė�����[�߂邱�Ƃ��ł���B�܂��A���g�̊Ō�X�L������ɂȂ���@��Ƃ��邱�Ƃ��ł��� | 1. �������ł̊Ō�̌��̒��ŁA�������Ƃ̈Ⴂ�⋤�ʓ_�A���ғ����𗝉����� 2. �������ł̊Ō�̌���ʂ��āA���g�̊Ō�X�L����U��Ԃ�@��Ƃ��� �y���C���@�z �������ł̎����o�� | 8�� �i2023�N�x�V���E���Ώہj |
�E�������̓x�b�h��ʼn߂������҂��������A���C��a���͊��҂����R�Ɏv���v���ɉ߂����Ă���A�f�C���[�����ɂ�����Ă����B�]�|�]�����Ȃ��悤�ɁA���ҌX�̏K���Ȃǂ����L���Ă����B �E�������ɔ�������������Ȃ��������A���@�����Ȃ���̑Ή�����������B�����Ή����o�����邱�Ƃ��ł����B���@��3�`4��/�����������A���@�シ���Ƀ��n�r���X�^�b�t��ADL�]���ɂ�����A�h�{�m��������A�X�s�[�h�����������B |
|
| ̫۰���ߌ��C�T | �Ō� ���E�� | �V���E���Ƃ��Ċ����邱�Ƃ����R�Ɍ�荇�����ŁA���育�Ƃ��肪�������L���A�E����z���đ��k��������W�����ł��邱�ƂŁA�A�J���͂ɂȂ��邱�Ƃ��ł��� | 1. �s����炳�����z���邽�߂̐�y�����̒m�b���w�Ԃ��Ƃ��ł��� 2. ���ԂƂ��đ��k��������W�������邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z l ���E�퍇�����C l ��y�E���̑̌��k�u l �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� | 6�� | ���C�̗l�q�́w�Ō암�u���O�x�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B �ȉ����A�N�Z�X���Ă��������B https://www.keijinkai.com/jyouzankei/topics/2024/07/04/ |
|
| ̫۰���ߌ��C�U | �Ō� ���E�� | 1. ���ԂƋ��ɁA���N�x�̊w�т�o����U��Ԃ�A���g�̍���̃L�����A�ɂ��čl���� 2. �Q�N�ڂ��}����ɂ������Ă̐S�\��������ɂ��Č��ꉻ���� �y���C���@�z l ���E�퍇�����C l �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� | 3�� | ���C�̗l�q���w��R�k�a�@Instagram�x�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B QR�R�[�h���A�N�Z�X���Ă��������B ��6��30�����e�̐V�l�t�H���[�A�b�v���C��QR�R�[�h���f��
|
||
| ���_�[�� | ||||||
| �ċz�P�A���C �i��b�ҁj | �Ō� | �T | �ċz��Ԃ̃A�Z�X�����g�\�͂̌����}��A���ҏɉ������ċz�P�A�̕��@�𗝉����� | 1. �ċz��̉�U�����𗝉����� 2. �ċz�̊ώ@�𐳊m�Ɏ��{���� 3. �ċz�̃A�Z�X�����g�ɂ��ė������� �y���C���@�z l �u�` l ���K | 10�� |
�E"�Ǐ�ώ@�����鎞�ɁuOPQRST�v�Ƃ�����f���@�����邱�Ƃ��w�B�x�Ƌ��s�̈ʒu�W�ŁA��t�Ɖ��t�̋�̓I�ȋ��E����Y�ꂩ���Ă��̂ŁA���߂Ċw�ׂ��B�X�N�C�[�W���O�����H���Ă݂���A�������̌����邱�Ƃ��o���ėǂ������B �E�ċz��̊�b����ēx�w�ђ������Ƃ��ł��A�X�N�C�[�W���O�̕��@���w���Ƃɂ��A�Տ��ł��T�N�V�������K�v�Ȋ��҂���ɍs���A�����悭�A�����ł����҂���̋�ɂ�����悤�Ɏ��{���Ă��������B �E��b�҂͏����I�ȃA�Z�X�����g�̍u�`�ł���A�o�������Ȃ��Ō�t�ɂ��킩��₷�����e�ł��������߁A�V���҂Ɏw������ꍇ�ɓ��l�ɓ`���Ă��������Ǝv�����B |
| �ċz�P�A���C �i���H�ҁj | �Ō� | �U | �l�H�ċz�푕�����̊��҂̊ώ@�ƃA�Z�X�����g�ɕK�v�Ȓm���E�Z�p���K������ | 1. �l�H�ċz�푕�����҂̊ώ@�|�C���g�𗝉����� 2. �l�H�ċz�푕�����҂̃A�Z�X�����g�ɂ��ė������� 3. �l�H�ċz�푕�����҂̊ώ@�A�A�Z�X�����g�̊w�т����ۂ̃P�A�Ɍ��т��邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z l �u�` l ���K l �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
�E�ċz��̐ݒ�ɂ��āA���Ȃ藝�����[�܂����B �E�l�H�ċz�푕�����҂̊ώ@�_�ȂǁA���Ҏ��g�ł͑i���邱�Ƃ͂ł����A�ċz��ԈȊO�ɂ��S�g��Ԃ̊ώ@����ł���Əڂ����w�Ԃ��Ƃ��ł����B �E�X�ɓK�����ċz�탂�[�h�̌������ƃ��J�j�Y�����w�ׂ��B����Ő�������t�B�W�J���A�Z�X�����g����Z��U��Ԃ鎖���o���A�܂��A�Z�X�����g�̉ۑ���L���Ă�����l�@���w�ׂ��B |
|
| �Ō�ߒ����C | �Ō� | �T | ���ጟ����ʂ��Ď��g�̊Ō���H�ɂ����鋭�݁E��݂�m�鎖�ŁA�Ō�͌���ɂȂ���@��Ƃ��� | 1. �Տ���ʂ�z�肵�����ጟ����ʂ��A���g�̊Ō���H��U��Ԃ�A���҂ɂƂ��čœK�ȊŌ���l���邱�Ƃ��ł��� 2. ���g�̋��݁E��݂����A����̂��ǂ��Ō���H�ɂȂ���@��Ƃ��� �y���C���@�z l �u�` l �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� | 12�� | �E�����������čs�����邱�Ƃ��ɂ��ĊŌ���s���Ă��������Ǝv���܂��B �E���O�w�K�̃A�Z�X�����g�̉ۑ���܂ߋv�X�ɂ�������Ō�ɂ��čl���邱�Ƃ��o�����Ɗ����܂��B�O���[�v���[�N�ő��̓����̍l����A�t�@�V���e�[�^�[����̏����ɂ��l�����L����A����̊Ō�P�A�Ɋ������Ă��������Ǝv���܂����B �E�Ō�t�ɂȂ��Ă���Ō�ߒ��������������Ă݂ĕ��i��������Ɛ[���l���悤�Ǝv�����B |
| ���E��Q���^ | ||||||
| �ېH���������C �i��b�ҁj | �Ō� ��� ���E�� | �T | ���S�ȐH���������s�����߂ɕK�v�Ȋ�b�I�m���Ƒԓx���K������ | 1. ������u�H�ׂ�v���Ƃ̈Ӌ`�𗝉����� 2. �ېH�E�����̃��J�j�Y���𗝉����� 3. �ېH�E������Q�������҂ɋN����₷�����X�N�Ƃ��̏Ǐ�𗝉����� 4. ���S�ɐH������s�����߂̕��@�𗝉����� �y���C���@�z l �u�` l ���K | 9�� |
�E�ېH�����̂����݂ɂ��ė����o���� �E�A�p���A���̐l�ɂ������H�`�Ԃ̑I�̓����m��܂������ώ@�̑����Ɋ����܂����B �E���҂���̚����@�\���l�����āA�ېH�����^���̂ǂ̒i�K�ł���̂����Ȃ���H������邱�Ƃ���ł��邱�ƁB�����������ł��H���`�Ԃ��Ⴄ���ƂŐ�G��□���Ⴄ�悤�Ɋ����邽�߁A���҂���5���ŐH�����y���ނ��Ƃ��ł���悤�A�H���������A���j���[��`���Ȃ������邱�Ƃ��厖�ł��邱�Ƃ��w�т܂����B
|
| �ېH���������C �i���H�ҁj | �Ō� | �T | �ېH�E�����̍����ɂ��ĐU��Ԃ�A���S�ȐH���������s�����߂̒m���Ƒԓx���K������ | 1. ��u���̌o����������ƂɁA���̑ΏۂɕK�v�ȃA�Z�X�����g�A�P�A���@���v�l���邱�Ƃ��ł��� 2. ���C�ł̊w�т��A���H�ɓK�����邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z l �u�` l �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� | 11�� |
�E�a�ԁA�N��A�����?�H�����A�ЂƂЂƂ����܂������͂����邱�ƂŁA�����Ɛ[���������Nj��ł�������ɂ������邱�Ƃ��w�B�����Y�݂������a���̊Ō�t�����Ƒ�R�̈ӌ������A�����ł������Ƃ��傫�������B �E�H��������邤���ŁA������肾���ł͂Ȃ��H���p���⎾���̐i�s�A���o���̏�ԂȂǂ��A�Z�X�����g���ĐH����̕��@����������K�v������Ɗw�B �EST�̋��͂Ȃ���a���Ŏ��H���Ă��������L���ł������Ƃ킩�����B�H���O�̌��o�P�A�������ɊW���鎖���ܓ��^�ŐH�~���i����ꍇ������Ɗw�B�܂������H�̓�Փx��������ƐH�~�ቺ���鎖�����鎖���킩�����B�y�������S�ɐێ悵�Ă��炤���߂ɐH�����Ԃɂ��Ă̍Œ���H���̌������K�v�ł���Ɗw�B
|
| �����ײ̹����C | �Ō� ��� ���E�� | �U | �I�����ɂ��銳�ҁE�Ƒ��ւ̑�������ѐl���d�����P�A�ɂ��ė������� | 1. �I�����̊��ҁE�Ƒ��P�A�ɂ��ė������� 2. �A�h�o���X�E�P�A�E�v�����j���O�iACP�j�̊�{�T�O�ɂ��ė������� 3. ���g���l����I�����P�A�ɂ��ďq�ׂ邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z l �u�` l �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� | 7�� |
�y��u���̊w�сz �E���Ȍ��肪�ł��Ȃ����ł��A���̐l�̂��̐l�炵���A���l�ςȂǂ��l���đ��E��Ŏx������ƌ��������w�т܂����i�Ō�t�j �E���Җ{�l�A�Ƒ�����ɂ��Ă��鉿�l�ςd���Ă������Ƃ��d�v�Ƃ������_�������Ƃ��ł����B�i�Ō�t�j �E���̐l�炵����m��ɂ͘b�����������邱�Ƃ���̋C�Â��ɂȂ邱�Ƃ��w�т܂����B���̂��߂ɂ͐M���W��z���Ď����̑z����b���������邱�Ƃ�A���҂��M�����Ă���l����������L���ă`�[���Ŋւ���Ă������Ƃ���ɂȂ�Ɗw�т܂����B�i��ƗÖ@�m�j �E���҂����̐l�炵������S�����邽�߂ɁA�`�[���ň�̂ƂȂ��Ďx�����邱�Ƃ��K�v���Ǝ��������BMSW�̗���Ƃ��ẮA���҂���̐����������ɂ��Ă��邱�Ƃ���������ɂ��Ă��������Ǝv�����B�ʐڏ�ʂł́A���҂��a����ǂ̂悤�ɔF�����Ă��邩�A�×{�����ɂ����đ�ɂ��������Ƃ͉����A�l���ɂ�����ڕW�͉����ȂǁA��̓I�ɒ������Ƃ��ӎ����Ă��������B�iMSW�j |
| �މ@�x�����C �i���މ@�x���j | �Ō� | �V | �މ@�x���ɂ��Ă̊�{���w�сA�Ō�E�Ƃ��Ďx���̓��e����H���w�Ԃ��ƂŁA��葁������މ@�x�����H���s���A�����ł����S�E���S�Ŋ��Җ����̍����×{�x���ɂȂ��邱�Ƃ��ł���B | 1.�u�`��ʂ��āA�މ@�x���̊�{�I�Ȓm���邱�Ƃ��ł��� 2.�Ō쌻��ł̑މ@�x���̎��H���C���[�W���A����̗×{�x���ɂȂ��邽�߂̈ꏕ�Ƃ��邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z ���u�` ���O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
1�� | �E�n���P�A�a���ł͌���ꂽ���@���Ԃ̒��őމ@�x����i�߂Ă����Ȃ���Ȃ炸�A���@��������������ߎx�����Ă������Ƃ��K�v�B���ݎ��{���Ă���މ@�O�̉Ƒ��w���A�މ@�O�J���t�@�����X�ɂ�鑽�E��Ƃ̘A�g���x���Ƃ��đ�ł��邱�Ƃ��Ċm�F�ł������ߌp�����Ă��������B �E�މ@�x���Ɋւ����{�I�Ȓm�����w�сA���@�Ɠ����ɑމ@�x�����n�܂��Ă��邱�Ƃ�m�����B���E��ŃO���[�v���[�N�ł��A�F�X�Ȉӌ����������Ƃ��ł��Ă������悩�����B
|
| �މ@�x�����C �i�ݑ�×{�x���j | �Ō� | �U | �މ@�x���Ɋւ����{�I�Ȓm����m��A�x���҂Ƃ��Ă̖�������H�𗝉����邱�ƂŁA�x���̕K�v�Ȋ��ҁE�Ƒ����ւ̑Ή��Ɋ��������Ƃ��ł��� | 1.�މ@�x���Ɋւ����{�I�Ȓm���◬��ɂ��ė������邱�Ƃ��ł��� 2.�a���Ō�t�Ƃ��āA���g�⑽�E��̖����A���H���e�𗝉����邱�Ƃ��ł��� 3.�x���̕K�v�Ȋ��ҁE�Ƒ����ɑ��āA�K�v�Ȏx�����C���[�W���邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z ���u�` ���O���[�v�f�B�X�J�b�V���� |
2�� | �E�����m��A�m�낤�Ƃ��邱�ƂŁA���̕������߂Ă��邱�ƂɋC�Â����Ƃ��ł��A���ǂ��P�A�ɂ��đ��k�ł��邱�Ƃ��w�� �E���Z�ȓ���ɂ��A��Î҂Ƃ��āA�w�Ȃ�̂��߂Ɂi�p�[�p�X�j����Ă��邩�x�l���邱�Ƃ�Y��Ă����B���S���čݑ��{�݂ʼn߂�����悤�a�@�@�\���K�v�Ȃ��Ƃ����߂ċC�t�����ꂽ�B �E���̕��̉��l���ɂ��A���p�҂������̐l�������邽�߂̈ꏕ�Ƃ��ăT�|�[�g���Ă������Ƃ�����Ɗ����܂����B
|
| ���\�[�X | ||||||
| �F�m�ǃP�A���C �i��b�ҁj | �Ō� ��� | �T | ���@�œ����Ō�E���E�Ƃ��āA�F�m�ǂɂ��Ă̒m�����K�����A�Ώێ҂Ɍ���Ă���Ǐ�ɂ��ăA�Z�X�����g���o���A�Ǐ�ɉ������Ō�A��삪�ł��� | 1. �F�m�ǂ̑�\�I��4�̎����𗝉����� 2. 4�̎����̊Ō�E���̓����𗝉����� �y���C���@�z l �u�` | 5�� | �E���X�̋Ɩ��Ŋ��҂���ւ̑Ή������J�ɏo���ĂȂ��ƍl���������錤�C�ł����B �E�Z�������ȂǁA���x���i�[�X�R�[�����Ȃ�Ɨ]�T���Ȃ��A�����������őΉ��������ł����B�u�`�Ŏ��グ��ꂽ����Ǝ����o�������Ă����̂ŁA���҂����1�l�ʼn����o��������ʂĂČĂ�ł���ȂƊ����܂����B�F�m�ǂɂ��l�X�Ȏ�ނ����邱�Ƃ��Ȃ�Ƃ��͊o���Ă��܂������A�ЂƂЂƂǂ�ȓ��������邩�����ċƖ��Ɋ������Ă��������ł��B�܂��A����͉�앟���m�̎��i����肽���Ǝv���Ă���̂ŁA���̍ۂɂ��m������������悤�w�͂��Ă��������Ǝv���܂��B �E���߂ĔF�m�ǂ̌��C�ɎQ�����܂����B4��ނ���F�m�ǂ��ڂ����w�Ԃ��Ƃ��o���܂����B�܂��A�a���ɂ��F�m�ǂ̊��҂��������邽�߁A����̊w�т���X�̋Ɩ��Ŋ�������悤�Ɋ撣���Ă��������ł��B
|
| �F�m�ǃP�A���C �i���H�ҁj | �Ō� ��� | �U | ���@�œ����Ō�E���E�Ƃ��āA�F�m�ǂɂ��Ă̒m�����K�����A�Ώێ҂Ɍ���Ă���Ǐ�ɂ��ăA�Z�X�����g���o���A�Ǐ�ɉ������Ō�A��삪�ł��� | 1. �F�m�ǂ̐l�̗�����[�߁A�Ή����@���l�����H�ł��� 2. �R�~���j�P�[�V�������@�ɂ��ė������A���H�ł��� �y���C���@�z l �u�` l �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� | 10�� | �E�F�m�ǂ̕��̔��������ł͂Ȃ��A�s����������ăP�A���l���Ă������Ǝv�� �E����������X�e�b�v�ōl���Ă������Ǝv�����i�p�[�\���Z���^�[�h�P�A�̎��H�j �E�p�[�\���Z���^�[�h�P�A�̎��H��a���ł�����������ǂ��ȂƎv���܂����i�y�������C�ł����j �E���̕��̃j�[�Y���l���A�O�Ȃ炢�̃P�A�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�X�̊��҂���ɍ������Ō����Ă��������B |
| �F�m�ǃP�A���C �i���ጟ���ҁj | �Ō� ��� | �U | 1. �F�m�NJ��҂�����������@�m���A�Ō�ߒ����g���Ė��������ł��� 2. �F�m�NJ��҂̖����`�[���ɂȂ������邱�Ƃ��ł��� | 1. �F�m�NJ��҂̊Ō�A���ɂ����Ăǂ�Ȗ�肪�����Ă��邩�A������p���đ����邱�Ƃ��ł��� 2. �������ɂ����āA���ԂƖ������L���邱�Ƃʼn����ł���Ƃ����̌������邱�Ƃ��ł��� �y���C���@�z l �u�` l �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� | 11�� | ���@�ɓ��@����Ă����A����ς���эs���S���Ǐ�̂��銳�҂ɂ��Ď��ጟ���������Ȃ����B���ጟ�����s���O�ɃA�Z�X�����g���@�ɂ��ču�`���s���A���̌�A�O���[�v�Łw���҂̏�ԃA�Z�X�����g�x�w��Ԃɉ������P�A�x�̎��_�ŃO���[�v���[�N���s�����B ���C�Q���҂̃��f�B�l�X�̈Ⴂ�ɂ�莖�O�u�`�����ł̓A�Z�X�����g���\���ɍs���Ȃ��Ƃ�������������A�t�@�V���e�[�^�[�i�F�m�NJŌ�F��Ō�t�j�̎w�����Ȃ��烏�[�N��i�߂Ă������B �܂��A����ςɊւ���g�̓I�A�Z�X�����g�ɂ��Ď�u�҂���̈ӌ������Ȃ��A�a�ԗ����ւ̉ۑ肪���炩�ƂȂ����B |
| �L�����A�x�� | ||||||
| ���E���Z�p���C | ��� | ����ʂɂ�����ϗ��I�ւ���U��Ԃ�A����̃P�A�̏�ʂɊ��������Ƃ��o����B | ���ނ����ɂ�������Z�p�Ɨϗ��I�z���ɂ��ė����ł���B �y���C���@�z l ���K l �O���[�v�f�B�X�J�b�V���� | 4�� 10�� |
�y�V�K�̗p���i�̎�舵���Ɋւ���w�K��z�F4���J�� �V�K�ō̗p�ƂȂ������ނɂ��āA��{�I�Ȏg�p���@�������[�J�[�̃A�h�o�C�U�[����w�������B��u�����E������́A�u�w�����Ă�������Ƃ���ɂ��ނ��g�p���邱�ƂŁA�A�R�ꂷ�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����v�u���܂ŔA�R�ꂵ�Ȃ��悤�Ƀp�b�g��]���Ɏg�p���Ă������A����w���@�����H���邱�Ƃŗ]���ȃp�b�g���g���K�v���Ȃ��Ȃ����v�ȂNJw�т��P�A�̉��P�Ɍq�����Ă��鐺������������Ă��܂��B
�y�Z�p���C�z10���J�� ���K�Ŏ��ۂɊ��ґ̌����邱�ƂŁA���҂������Ă���ł��낤�s���E��ɓ���m�邱�Ƃ��o�����B�܂��A���ނ̐��������ĕ��̍Ċm�F��e�R��h�~�̍H�v�Ȃǂ�m��@��ƂȂ����B���K��̃O���[�v���[�N�ł́A���҂́g㵒p�S�֔z�������������h�ւ̈ӎ��ȂǗϗ��ʂł̋C�t�����܂߁A����̃P�A�Ɋ�������ӌ��A���z���b���ꂽ�B �s��u���̐��t �E���ނ����A�M���W�A�b�v�Ɋւ��đ̌��o���������w�тɂȂ����B �E�����ő̌����鎖���o���ėǂ������B���ꂩ����I���c�����A�x�b�h�A�b�v�̍ہA�������ɋC�����ăP�A���Ă��������B �E����Ă������ł��A���X�̋Ɩ��̒��ŖY��Ă��镔���ȂNjC�Â����Ƃ��������B
�y����Z�\�E���ɑ���Z�p���C�z�F11���J�� 1���ɓ��E��������Z�\�E����ΏۂɁA�u���Z�p�v�u���{��̗����v�u�R�~���j�P�[�V�����v���m�F���邱�Ƃ�ړI�ɊJ�Â��܂����B����Z�\�E��2��1�g�Ŋ��҂Ɖ��҂�̌����Ȃ���A�w��w�̐��@�x�w�X�߁x�w�̈ʕϊ��x�w�x�b�h���㎞�̔w�����x�w�Ԃ����̓_���x�ɂ��ĐU��Ԃ�܂����B�܂��A�������̊��҂���ւ̈��A������̃^�C�~���O�A���t�g���Ȃǂ��U��Ԃ�܂����B |
|
| ��ر�x�����C�U �i�l�ތ𗬌��C�j | �Ō� | �V | 1.�}�������疝�����A�ݑ�×{���̑��@�\�^�Ō�i�������͋}�����Ō�j�̌���ɐG��A������(�{��)�Ƃ̘A�g���l���鎖�ŁA���X���[�Y�ȊŌ�A�g�����H�ł��� 2.���҂̑މ@��̗×{�����̏���m�邱�ƂŁA�e�����҂Ƃ��Ă̊��ҁf�̎��_�ŊŌ�����H�ł��� 3.���g�̊Ō�̐U��Ԃ�̋@��Ƃ��A����̃L�����A�f�U�C����`���ꏕ�Ƃ��邱�Ƃ��ł��� | 1.�������i�{�݁j�ƘA�g���Ë@�ւ̊Ō�Ƃ̂Ȃ�����w�Ԃ��Ƃ��ł��� 2.�������E���@�\�^�Ō�i�}�����Ō�j�̎��ۂ��w�Ԃ��Ƃ��ł��� 3.���ꂼ��̋@�\�ɉ��������E��Ƃ̘A�g�݂̍�l��m�邱�ƂŁA�`�[����Âɂ��čl����@��������Ƃ��ł��� 4.���҂̗×{��m��A����̎��g�̊Ō�ɐ��������Ƃ��ł��� �y���C���@�z l �A�g��Ë@�ւł̃V���h�[���[�N �i3���ԁj | 9�� |
�E���߂Č����l��a�@��PNS�i�p�[�g�i�[�V�b�v�E�i�[�V���O�E�V�X�e���j�̓����o�[�̈ӌ��d�����Ō�V�X�e���ł����B�Ō�X�^�b�t�X�����[�_�[�̂悤�ɓ����Ă��Ċ������܂����B
|
| �Ō�Ǘ��Ҍ��C | �Ō�t�� | 1.�Ō�Ǘ��҂Ƃ��ĕK�v�Ȏp���A��{�I�Ȓm���E�Z�p�Ƃ��Ẵ��t���N�V�����̎�@�Ǝ��H�|�C���g���w�� 2.�u�T�O���v�u���́v��g�ɂ��邱�Ƃ��ӎ����Ċw�� |
�E���t���N�V�����i���ȁj�Ɣ��Ȃ̈Ⴂ��m�� �E�Ō�}�l�W�����g���t���N�V�����̊T�O�𗝉����� �E�Ō�}�l�W�����g���t���N�V�����̎��H���@���w�� �y���C���@�z �Ee-���[�j���O��p�������Ȋw�K �E�O���[�v���[�N |
5�� 7�� 8�� |
�E�������烊�t���N�V������S������悤�ɂȂ����B �E�O���[�v�����o�[�̎���ł����Ă��A������������Ǝv���Ȃ���f�B�X�J�b�V�������邱�ƂŁA����������g���čl���邱�Ƃ��ł����B�܂��A�O���[�v�����o�[�̂��낢��ȍl�������Ƃ��ł��Ă悩�����B |
|